あれやこれやが重なるとブログが書けなくなります。ずるずる引きずりそうなので、完全に日記を書くことにします。
トマトの芽かきは最初が肝心だ
動画で学んだトマトの芽かきチャレンジするものの、時期が遅すぎてかなり難しかったということ。
別れ枝が多すぎると、枝が広がりすぎて収穫できなくなるので初めて挑戦した芽かき作業。4月に植えたトマトも2ヶ月経てばかなり成長しているので、どれが別れ枝かがわからないぐらいにジャングルになっていた。
🍅🍅🍅
時すでに遅かったようにも思うが、大胆に枝を落としまくった。この結果がわかるのは数週間先。
高齢の両親を万博に連れて行く
舞洲駐車場に停めてシャトルバスで向かいました。車椅子利用なので、スタッフの方も丁寧に対応していただけます。

車椅子で両手が塞がっているので、ほとんど写真が撮れませんでした。

14時に入場して19時に出場。

入ったパビリオンはカタール館と住友館。住友館の映像作品は素晴らしかった。
「生物と無生物のあいだ」
サバ (id:savatrunk)さんにおすすめしてもらった本を読みました。
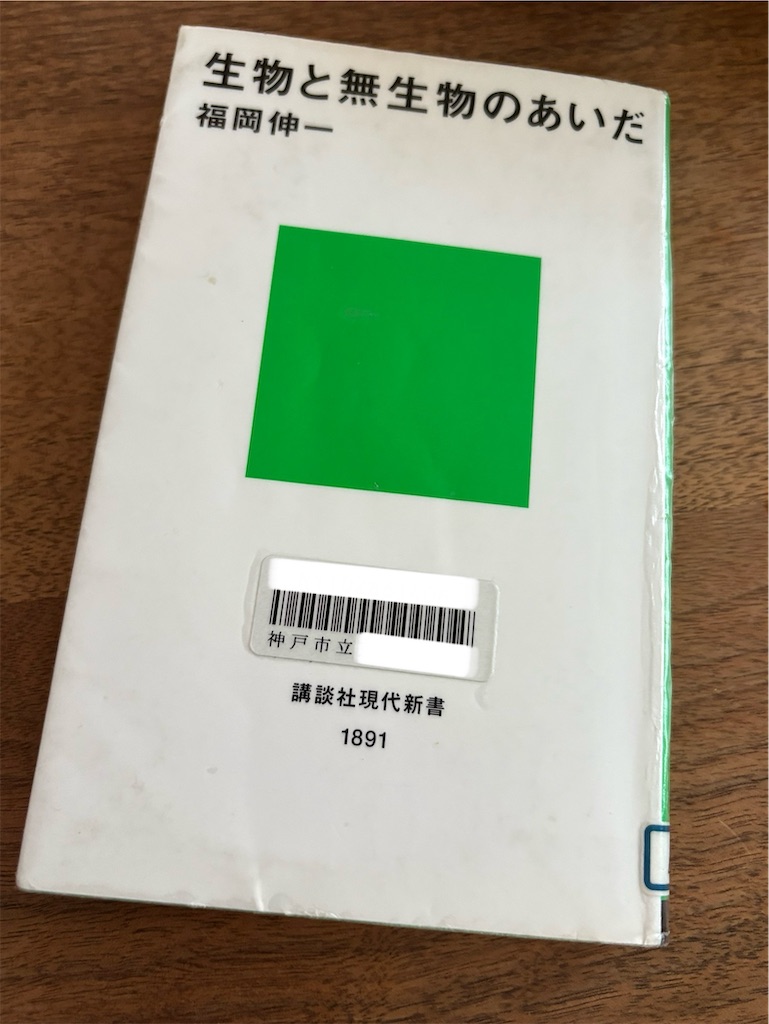
アメリカで研究をされていた頃、見聞きした話し、遺伝子研究の先人の話、ご自身の遺伝子に関する研究など大変興味深い内容でした。
印象深かった話しは次の通り。
日本では旧紙幣にも採用されるなど英雄扱いされている野口英世、その業績には疑問が残ることが多く、アメリカでは評価されていないこと。
遺伝子の二重らせん構造を発表したワトソンとクリックは、他の研究者の査読前の論文を見ちゃって、二重らせんを発表しちゃった疑惑。
福岡氏が行った遺伝子操作の研究で、GP2というタンパク質は膵臓の機能において重要な役割を果たすと予測され、「GP2遺伝子を欠損させたマウスを作れば、膵臓に顕著な障害が出るだろう」と考えられていました。分子生物学の技術を使い、GP2の遺伝子を完全に削除した「GP2ノックアウトマウス」が作られたが、驚くべきことにその完全欠損マウスは、見た目も成長も健康状態も「ほとんど普通のマウス」と変わらなかった。
ある部品(GP2)が失われても、別の経路や調節によって機能が補われ、生命が全体として維持されることを示しており、この実験が、福岡氏が動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)という言葉を強く意識した発端になったのだろう。
